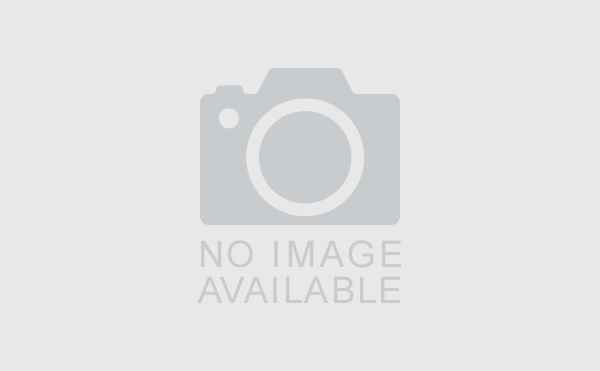この言葉・・説明できますか?
uchyさんからご質問を頂きました。
姿勢についての用語の意味は?
確かに、滑走中の姿勢にはいくつかの表現があります。
それぞれについて、ayim的に解説してみましょう!
1.内倒(ないとう)
これは、ダメな滑走姿勢として良く出てくる言葉です。言葉としては、内側に倒れているという言葉ですが、ターンを伴う滑走スポーツは必ず内側に倒れます(スキーや自転車等など)。では、なぜダメなのかというと必要以上に傾いている。だからダメなのだと・・。でもこれでは納得できませんよね?
これを説明するためには、体軸と重心いうことを理解する必要があります。
体軸・・直立したときに体の中心を通る仮想の軸線。頭から背骨を通る直線という感じです。
重心・・物体のバランスを取ることができる中心点。人体で言うと、おへその辺りです。
体軸をターンしたい方向に傾けるとボードはターンを始めます。でも実は、体軸が傾くからターンするのではなくて体軸が傾くことによって重心がターン方向に移動するから、ターンをするのです。
でも、内倒というのは、体軸を傾けるけど重心が動いていない状態(もしくはあまり動いていない状態)を指します。具体的に言うと、上半身だけ傾いている(上半身は傾いているが、重心である腰はボードの真上)。もっと上半身を傾ければ、重心は引っ張られて移動しますが、必要以上の上半身の傾き・・・これを内倒と表現します。
2.内傾(ないけい:リーン)
これは、内倒でほぼ説明してますが、ターンをするために必要な、体軸を傾ける事です。体軸を傾けることで重心が移動してターンをする。ターンに必要量の傾きをしていること。を意味しています。イメージとしては、関節を固定した直立の状態で、体の傾きだけでターンする感じです。
3.内向(ないこう:ローテーション)
言葉としては、内側に向くこと。向けること。基本姿勢から見て、上体をターン内側に向けること。
上半身と下半身はつながっているので、上半身を大きく右に捻(ひね)れば、下半身も右回転しようとついてきます。これが、回転力になります。この回転力のことを、順捻り(=ローテーション)と言っています。ターン中に、上半身を大きくターン内側に捻り込めば、下半身がついてくるのでボードも大きく捻った方向にずれ回ってきます。内向する=ローテーションする。と同じ意味で使っています。
4.外倒(がいとう)
残念ながら、この言葉は存在しません。(はずです・・)
5・外傾(がいけい:リーンアウト)
言葉の意味としては、内傾(リーン)に対して、バランスを取るために上体をターン外側(アウト)に起こすことです。
実は、内傾をし続けるにはかなり特殊な状態でないと実現できません。それは、摩擦のないスケートリンクで頭を頂点とした円錐(えんすい)を作るようなスケート選手のような状態です。スノーボードのような重力を使う滑走スポーツでは不可能です。また、この状態は遠心力とのバランスを取ってしまうため、その他の変化に対応ができない状態になってしまいます。そこで上体を起こすのですが、その起こし具合で、スピード、斜面変化、斜度変化、雪質変化に対応していると思われます。なぜ上体を起こすことでバランスが取れるのかというと、上体を起こすことで円錐の頂点の位置が変わり、そこに働く遠心力の大きさを変えることができるのではないか?とayimは予想しています。雪上実験したわけではないので証明されていませが、物理学的には、回転半径が小さいほど遠心力は大きくなります。
6.外向(がいこう:逆ローテーション)
内向に対する外向です。ターン外側に上体を向けること。です。
内向と違うのは、重心の位置と向きを変えないように上体を回転させることです。そのためには、下半身が逆回転する必要があります。下半身を逆回転させるということは、ボードの方向を変える回転力があるということを意味します。内向のときは、上体の回転方向にボードが回りますが、外向のときは、向いた方向とは逆回転をします。実際は、ボードの向きに対して上体の向きを考えるので、ニュートラルポジションに対して、上体がターン外側に向いているため、外向という表現をします。
7.アンギュレーション(くの字の姿勢)
教程本的には、外向傾姿勢と言います。外傾と外向をミックスした姿勢です。ターン中のバランスを取るための外傾と、ターン外側に働きかけるための外向を同時に行っています。くの字姿勢というと外傾だけを意味しそうですが、アンギュレーションと同じ意味で使っているので、外向傾が正しいと思います。がしかし、この言葉は、カービングが一般的になる前から使われている言葉なので、現在は、アンギュレーション=外傾が正しいのでは?とayim的には思っていますが、一般的ではないので、その辺は使い方に注意が必要です。
と以上。説明しましたが、これはあくまでayim的な解釈の元で述べています。図があればもうちょっと分かりやすいと思いますが、今回はこの辺で勘弁してください!
違うんじゃないの?という意見もあるかもしれませんが、それはそれで良いと思います。滑走理論はいろいろあって、言葉の解釈もいろいろあると思いますので、独自の理論をお持ちの方は、その理論を突き通してください!