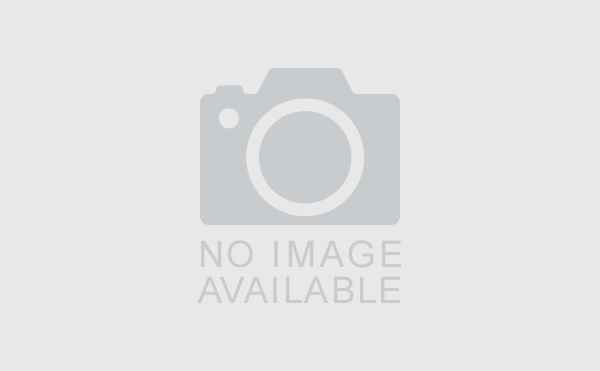ドリフト2
ドリフトの滑走理論につながる基礎知識を説明したいと思います。
あらかじめお断りしておきますが、ここから先はayim理論による解説です。
一般論と違うところがあるかもしれません。
必要な部分だけを信じ、その他の部分は忘れるくらいの気持ちで読んでみて下さい。
まず、ドリフトは初心者の技術であるということです。
イントラ検定のドリフトは難しくて初心者のドリフトとは関連性無し。と思われがちです。
確かに初心者は何となくドリフトをしています。でも、受験者が何となくドリフトをしても合格点が出ない。
だから、そう言われるのではないかと思います。
でもayimはそう考えていません。
ドリフトは初心者の技術で、その洗練されたものが検定種目になっていると考えています。
では、その理由を述べます。
初心者がターンをするプロセスを考えてみます。
1・エッジの切り替え時、先落とし時
初心者にとって先落しとは、たいへん難しい技術でなかなか出来ないものです。そのために必要な動作は先行動作です。上体をターン内側に捻りこむ(内向)ことで先落しの回転力を発生させます。これはターンのきっかけを掴むためには必要な動作です。
2・先落し後
先落しによりきっかけは掴みましたが、フォールラインまではなかなか向かないものです。そこで逆ローテーション(外向)によって、フォールラインを超えるところまでテールを振ってボードの方向を変えます。初心者にとってフォールライン上は恐怖感を伴うものです。思い切ってテールを振ってサッとかわしたいものですよね。
3・ターン後半
逆ローテーションのままの姿勢でいると、ボードはコントロールできず不安定な状態になります。そこで、逆ローテーションを戻してターンを仕上げます。結果としてローテーションしている事になります。また、次のターンをするために必要な動作でもあります。
これが、初心者が行うターンの運動の基本になっていると考えています。
もちろん理論的には、ターン中盤の外向はターン外側に働きかけるため、ターン後半のローテーションはズレのコントロールをするため。など理由はいろいろありますが、初心者のターンとリンクさせるとこんな感じになります。
初心者は、これらの動きをすると、その通りにボードが反応しターンをします。
しかし、上級者はそんなことをしなくてもターンができるし、極端に言えば、足首の微妙なコントロールだけでもターンができます。だから、検定の動きは無意味になってしまい。わざとらしい動きになってしまうんです。それでは合格点は出ないと思います。
まず大切なのは初心者のターンをよく観察すること。
よく見ると少ないバランスの中で無駄なことはしてないですよ。だって無駄なことをすると転んでしまうから・・・初心者にとっては全てが必要な動きなんですよ。
練習法としては、
下半身でターンをしないこと。上半身の回転力だけでターンをしてみましょう。内傾をとってもいけません。ポジションがあっていればターンするはずです。
それができたら動きをスムーズにして・・・・
それができたらターン弧をコントロールする・・・・
かなり難しいです。だから上級者の技術なんです。と、考えています。